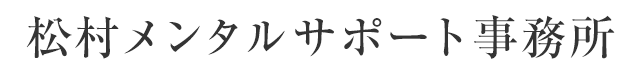【この記事を読むと分かること】
1.メンタルヘルス(心が健康)の本質が分かる
2.メンタルヘルス不調(心が不健康)の本当の意味が分かる
3.働くうえで何がストレスになるのか分かる
4.メンタルヘルス不調を効果的に防ぐ具体的な方法が分かる
4月は新たなスタートを迎える季節です。たくさんの新入社員が職場で初めての経験に挑み始めます。期待と不安が交錯するドキドキの季節ですね。
新入社員の方たちは、これから様々なことを学んでいくことになります。そんな学びの中にメンタルヘルスも仲間に入れてほしくてこの記事を書きました。
新入社員の方たちが健やかに仕事に取り組むことができるよう、メンタルヘルスの基礎知識と具体的な対処法についてご紹介したいと思います。
メンタルヘルスを理解しよう

初めに、メンタルヘルスとは何かについて理解しておきましょう。
世界保健機関や厚生労働省の定義などを手掛かりに、メンタルヘルスの本質に迫ってみたいと思います。
世界保健機関や厚生労働省の定義などを手掛かりに、メンタルヘルスの本質に迫ってみたいと思います。
世界保健機関(WHO)の定義
先ずは世界保健機関(以下WHO)が定めるメンタルヘルスの定義を見てみましょう。
WHOによるメンタルヘルス(心が健康)の定義
▶メンタルヘルスに関するWHOのホームページはこちら
WHOが定めているということで、地球上の全ての文化圏で受け入れることができる定義ですから、かなり抽象的です。何が書かれているかを整理すると以下となります。
◆個人が自分の可能性を実現し
◆日常のストレスに対処でき
◆生産性が高い状態で働くことができ
◆コミュニティに貢献できる良い状態
以上が、心が健康な状態であるとしています。外から観察できるものばかりで、内面の記載がありません。
WHOによるメンタルヘルス(心が健康)の定義
精神的健康とは、単に精神障害でないということではない。それは、一人ひとりが自らの可能性を実現し、人生における普通のストレスに対処でき、生産的にまた実り多く働くことができ、自らの共同体に貢献することができるという良い状態のことである
▶メンタルヘルスに関するWHOのホームページはこちら
WHOが定めているということで、地球上の全ての文化圏で受け入れることができる定義ですから、かなり抽象的です。何が書かれているかを整理すると以下となります。
◆個人が自分の可能性を実現し
◆日常のストレスに対処でき
◆生産性が高い状態で働くことができ
◆コミュニティに貢献できる良い状態
以上が、心が健康な状態であるとしています。外から観察できるものばかりで、内面の記載がありません。
※当事務所のカウンセリングの特徴と概要についてはこちらをご覧ください
※対面・オンラインでのカウンセリングのお問い合わせはこちらからどうぞ
厚生労働省の定義
次に厚生労働省の定義を見てみましょう。
厚生労働省によるメンタルヘルス(心が健康)の定義
▶厚生労働省の関連ページはこちら
厚生労働省によると、メンタルヘルス(心が健康)とは以下となります。
◇心が軽い
◇穏やかな気持ち
◇やる気が沸いてくるような気持ち
こちらは全て内面での出来事を表しています。このような気持ちでいることが、心が健康な状態であるとしています。
この厚生労働省の定義(内面)と、先ほどのWHOの定義(外面)を組み合わせると、メンタルヘルスの定義がより分かりやすくなりますね。
◇◇◇◇
実は厚生労働省では、「メンタルヘルス(心が健康)」の定義だけでなく、「メンタルヘルス不調(心が不健康)」も定義しています。見てみましょう。
メンタルヘルス不調(心が不健康)の定義
▶厚生労働省(こころの耳)のページはこちら
こちらもまだ抽象的ですが、何が書かれているか整理してみましょう。
心が不健康とは、
「心身や生活に影響を与える精神的な問題と行動上の問題のこと」
この厚生労働省のメンタルヘルス不調の定義から、メンタルヘルス(心が健康な状態)を導き出してみましょう。
メンタルヘルス(心が健康)とは
◆「精神機能と行動に問題がない状態」
ここで新しい視点が見えてきましたね。メンタルヘルス不調とは精神的な問題だけでなく、行動上の問題も含まれることに注意してください。
厚生労働省によるメンタルヘルス(心が健康)の定義
メンタルヘルスとは体の健康ではなく、こころの健康状態を意味します。体が軽いとか、力が沸いてくるといった感覚と同じように、心が軽い、穏やかな気持ち、やる気が沸いてくるような気持ちの時は、こころが健康といえるでしょう
▶厚生労働省の関連ページはこちら
厚生労働省によると、メンタルヘルス(心が健康)とは以下となります。
◇心が軽い
◇穏やかな気持ち
◇やる気が沸いてくるような気持ち
こちらは全て内面での出来事を表しています。このような気持ちでいることが、心が健康な状態であるとしています。
この厚生労働省の定義(内面)と、先ほどのWHOの定義(外面)を組み合わせると、メンタルヘルスの定義がより分かりやすくなりますね。
◇◇◇◇
実は厚生労働省では、「メンタルヘルス(心が健康)」の定義だけでなく、「メンタルヘルス不調(心が不健康)」も定義しています。見てみましょう。
メンタルヘルス不調(心が不健康)の定義
精神障害や自殺のみならず、ストレスや強い悩み、不安など、労働者の心身の健康、社会生活及び生活の質に影響を与える可能性のある精神的及び行動上の問題を幅広く含むもの
▶厚生労働省(こころの耳)のページはこちら
こちらもまだ抽象的ですが、何が書かれているか整理してみましょう。
心が不健康とは、
「心身や生活に影響を与える精神的な問題と行動上の問題のこと」
この厚生労働省のメンタルヘルス不調の定義から、メンタルヘルス(心が健康な状態)を導き出してみましょう。
メンタルヘルス(心が健康)とは
◆「精神機能と行動に問題がない状態」
ここで新しい視点が見えてきましたね。メンタルヘルス不調とは精神的な問題だけでなく、行動上の問題も含まれることに注意してください。
※当事務所のカウンセリングの特徴と概要についてはこちらをご覧ください
※対面・オンラインでのカウンセリングのお問い合わせはこちらからどうぞ
より具体的なメンタルヘルスの定義について

より具体的にメンタルヘルスを理解したり対処法を考えたりするにあたって、もっと脳の機能や行動面に焦点を当てた定義が欲しいところです。
以下、先ずは体の健康、すなわち「臓器の機能」と「痛み(体の異変を伝える信号)」の二つの側面から、私なりの解釈とはなりますが、メンタルヘルス(心が健康)を定義づけしてみたいと思います。
以下、先ずは体の健康、すなわち「臓器の機能」と「痛み(体の異変を伝える信号)」の二つの側面から、私なりの解釈とはなりますが、メンタルヘルス(心が健康)を定義づけしてみたいと思います。
※当事務所のカウンセリングの特徴と概要についてはこちらをご覧ください
※対面・オンラインでのカウンセリングのお問い合わせはこちらからどうぞ
心が健康であるとはどういう状態か
心とか精神というのはとても抽象的であるため、ここでは体の健康からヒントを得たいと思います。
体が健康であるとは、各臓器が正しく機能し、かつ痛みがない状態といえます。これを心に置き換えてみましょう。
心の臓器とは脳ですね(たぶん)。脳が心や精神に対して持つ機能とは、「外界を客観的に認識し、生存確率を上げ、遺伝子をよりよく残す行動を選択する」ということです。
恐らく究極的には、この「生存確率を上げ、遺伝子をよりよく残す」という結果を成し遂げるために心は働いていると思われます。
次に痛みです。
体の痛みとはその部位に異変が生じていることを知らせる信号です。痛みによって体の異変を察知し、手当てし、動かさないようにして保護します。
では、心の痛みとは何でしょうか。心に異常を知らせる信号とは何でしょうか。
それが負の感情です。悲しみ、恐怖、不安、怒り、嫌悪などですね。
体が健康であるというのが、「各臓器が正しく機能し、痛みがない状態」であるとするなら、心が健康であるというのは、「脳が正しく機能し、負の感情がない状態」であるといえます。
より詳しく記述してみましょう。心が健康な状態とは、
これが、心が健康な状態といえるでしょう。
体が健康であるとは、各臓器が正しく機能し、かつ痛みがない状態といえます。これを心に置き換えてみましょう。
心の臓器とは脳ですね(たぶん)。脳が心や精神に対して持つ機能とは、「外界を客観的に認識し、生存確率を上げ、遺伝子をよりよく残す行動を選択する」ということです。
恐らく究極的には、この「生存確率を上げ、遺伝子をよりよく残す」という結果を成し遂げるために心は働いていると思われます。
次に痛みです。
体の痛みとはその部位に異変が生じていることを知らせる信号です。痛みによって体の異変を察知し、手当てし、動かさないようにして保護します。
では、心の痛みとは何でしょうか。心に異常を知らせる信号とは何でしょうか。
それが負の感情です。悲しみ、恐怖、不安、怒り、嫌悪などですね。
体が健康であるというのが、「各臓器が正しく機能し、痛みがない状態」であるとするなら、心が健康であるというのは、「脳が正しく機能し、負の感情がない状態」であるといえます。
より詳しく記述してみましょう。心が健康な状態とは、
◆強い負の感情がなく
◆外界を客観的に認識することができ
◆生存確率を上げ遺伝子をよりよく残すための行動を実践している状態
◆外界を客観的に認識することができ
◆生存確率を上げ遺伝子をよりよく残すための行動を実践している状態
これが、心が健康な状態といえるでしょう。
※当事務所のカウンセリングの特徴と概要についてはこちらをご覧ください
※対面・オンラインでのカウンセリングのお問い合わせはこちらからどうぞ
メンタルヘルス不調を定義づける
心が健康な状態が分かったところで、心が不健康な状態(メンタルヘルス不調)を定義づけしてみます。
私が考えるメンタルヘルス不調(心が不健康)の定義
そして、自分の生存にとって不都合な行動を長期にわたって実行していると、ストレス反応によって身体面に深刻な悪影響が出てきます。
代表的なものが、脳からの出血や突然の心停止です。
身体面の悪影響があるレベルを超えると最悪は死んでしまいます。そうならないように、この不都合な行動に強制的なストップをかけなければなりません。
そのための、あるカテゴリー(診断基準)に合致した状態が、ストレス反応性の精神疾患だと私は考えています。
私が考えるメンタルヘルス不調(心が不健康)の定義
強い負の感情によって外界を極めて主観的に理解するようになり、その結果、自分の生存にとって不都合な行動を選択して実行しているにもかかわらず、そのことに全く気づけなくなっている状態
そして、自分の生存にとって不都合な行動を長期にわたって実行していると、ストレス反応によって身体面に深刻な悪影響が出てきます。
代表的なものが、脳からの出血や突然の心停止です。
身体面の悪影響があるレベルを超えると最悪は死んでしまいます。そうならないように、この不都合な行動に強制的なストップをかけなければなりません。
そのための、あるカテゴリー(診断基準)に合致した状態が、ストレス反応性の精神疾患だと私は考えています。
※当事務所のカウンセリングの特徴と概要についてはこちらをご覧ください
※対面・オンラインでのカウンセリングのお問い合わせはこちらからどうぞ
精神疾患は生活習慣病?

ここでひとつの疑問が湧きます。
それは、不合理な行動にストップをかける機能がストレス反応性の精神疾患であるなら、それは病気ではなく、生存にとって必要な機能なのではないかということです。
この構図は糖尿病や肥満などに代表される生活習慣病に似ています。
もともと効果的だった機能が、近代化による社会環境の激変によって病気になってしまったという構図です。
例えば、かつてとても希少だった糖分を効率的に体内(細胞)に取り込む機能を、私たちは進化の過程で獲得してきました。この機能を私たちは今でも持っています。
しかし、砂糖(今は安価でたやすく手に入る!)であふれかえっている現代社会では、その機能が裏目に出て、糖尿病という形で私たちを苦しめることになってしまいました。
ということは、現代社会で問題となるストレス反応性の精神疾患も、もともと効果的な機能だった可能性があります。
それが急激な環境変化(近代化)によって病気となってしまったのではないでしょうか(例えば、「仕事を休むのは病気」、「寝て過ごすのは病気」など)。
ということは、適応障害や抑うつ状態など、労働者の間で現在流行している精神疾患(注:抑うつ状態は厳密には精神疾患ではありません)とは、生活習慣病の一種かもしれません。
こんなことは不可能ですが、もし社会全体が縄文時代と同じ生活様式に戻れば、現代のストレス反応性の精神疾患は、病気としては扱われなくなるでしょう。糖尿病はゼロになります。
それは、不合理な行動にストップをかける機能がストレス反応性の精神疾患であるなら、それは病気ではなく、生存にとって必要な機能なのではないかということです。
この構図は糖尿病や肥満などに代表される生活習慣病に似ています。
もともと効果的だった機能が、近代化による社会環境の激変によって病気になってしまったという構図です。
例えば、かつてとても希少だった糖分を効率的に体内(細胞)に取り込む機能を、私たちは進化の過程で獲得してきました。この機能を私たちは今でも持っています。
しかし、砂糖(今は安価でたやすく手に入る!)であふれかえっている現代社会では、その機能が裏目に出て、糖尿病という形で私たちを苦しめることになってしまいました。
ということは、現代社会で問題となるストレス反応性の精神疾患も、もともと効果的な機能だった可能性があります。
それが急激な環境変化(近代化)によって病気となってしまったのではないでしょうか(例えば、「仕事を休むのは病気」、「寝て過ごすのは病気」など)。
ということは、適応障害や抑うつ状態など、労働者の間で現在流行している精神疾患(注:抑うつ状態は厳密には精神疾患ではありません)とは、生活習慣病の一種かもしれません。
こんなことは不可能ですが、もし社会全体が縄文時代と同じ生活様式に戻れば、現代のストレス反応性の精神疾患は、病気としては扱われなくなるでしょう。糖尿病はゼロになります。
※当事務所のカウンセリングの特徴と概要についてはこちらをご覧ください
※対面・オンラインでのカウンセリングのお問い合わせはこちらからどうぞ
メンタルヘルスを悪化させるプライベート要因

新入社員の方に限りませんが、ここからは特に気をつけたいメンタルヘルス不調の要因をご紹介します。
まずはプライベート要因からです。
まずはプライベート要因からです。
仕事以外のプライベート要因
メンタルヘルス不調のプライベート要因には次のようなものがあります。
◇経済問題(借金や貧困 etc.)
◇健康問題
◇家族問題(非行、不仲、病気、介護 etc.)
◇事故
◇災害
◇犯罪被害 etc.
上記のことが自分の身に起きて仕事に行くのが難しくなったら、仕事に穴を開けることがないように、すぐに信頼できる人に相談してください。
予期せぬことが起きたときには、自分の心身の健康を守りながらも、仕事への悪影響も最小限に抑えること。これが、社会人にとって最も重要な振る舞いとなります。覚えておいてください。
それともうひとつ、プライベート要因として忘れてはならないのが、
◇遺伝要因
です。
詳しく見てみましょう。
◇経済問題(借金や貧困 etc.)
◇健康問題
◇家族問題(非行、不仲、病気、介護 etc.)
◇事故
◇災害
◇犯罪被害 etc.
上記のことが自分の身に起きて仕事に行くのが難しくなったら、仕事に穴を開けることがないように、すぐに信頼できる人に相談してください。
予期せぬことが起きたときには、自分の心身の健康を守りながらも、仕事への悪影響も最小限に抑えること。これが、社会人にとって最も重要な振る舞いとなります。覚えておいてください。
それともうひとつ、プライベート要因として忘れてはならないのが、
◇遺伝要因
です。
詳しく見てみましょう。
※当事務所のカウンセリングの特徴と概要についてはこちらをご覧ください
※対面・オンラインでのカウンセリングのお問い合わせはこちらからどうぞ
メンタルヘルス不調の遺伝要因について
メンタルヘルス不調や精神疾患は遺伝病ではありません。
しかし、精神疾患を発症した方の家族にも精神疾患の人がいるということを、私たち臨床家は経験上よく知っています。
精神疾患に関連しているとされる遺伝子は現在までに約200種類くらい見つかっています。
ただし、この遺伝子をひとつでも持っていれば何らかの精神疾患を必ず発症するというわけではありません(発症するには様々な条件が必要ですが、残念ながら詳しいメカニズムは分かっていません)。
そして、どのような症状の精神疾患が生じるか(すなわち、何という診断になるか)は、約200種類の遺伝子の様々な組み合わせによって決まるようです。
家族や親戚に精神疾患を発症した人がいる方は、これらの遺伝子のいくつかを受け継いでいます。
その遺伝子の組み合わせによっては、仕事上の様々なストレスがきっかけになって、精神疾患を発症してしまうリスクが高くなります。
しかし、精神疾患を発症した方の家族にも精神疾患の人がいるということを、私たち臨床家は経験上よく知っています。
精神疾患に関連しているとされる遺伝子は現在までに約200種類くらい見つかっています。
ただし、この遺伝子をひとつでも持っていれば何らかの精神疾患を必ず発症するというわけではありません(発症するには様々な条件が必要ですが、残念ながら詳しいメカニズムは分かっていません)。
そして、どのような症状の精神疾患が生じるか(すなわち、何という診断になるか)は、約200種類の遺伝子の様々な組み合わせによって決まるようです。
家族や親戚に精神疾患を発症した人がいる方は、これらの遺伝子のいくつかを受け継いでいます。
その遺伝子の組み合わせによっては、仕事上の様々なストレスがきっかけになって、精神疾患を発症してしまうリスクが高くなります。
※当事務所のカウンセリングの特徴と概要についてはこちらをご覧ください
※対面・オンラインでのカウンセリングのお問い合わせはこちらからどうぞ
メンタルヘルスを悪化させる職場の要因

次に職場の要因を見てみましょう。
メンタルヘルス不調を生じさせる職場の要因には次のようなものがあります。
メンタルヘルス不調を生じさせる職場の要因には次のようなものがあります。
長時間労働
残業時間が概ね月50時間を超えると、1日の睡眠時間が6時間を下回るようになります。
そして睡眠時間が1日6時間を下回ると、メンタルヘルスが悪化し始めることが分かっています。
残業する理由は様々です。上司からの命令の場合もありますし、顧客からの要求の場合もあります。あるいは、お小遣い稼ぎのための残業もあります。
悲しい話ですが、職場しか居場所がなく、帰宅したくないから残業しているという人もいます(あまり褒められる働き方ではありません)。
このようなダラダラ残業は必死に働いているわけではありませんのでほとんど疲れません。
したがって月に50時間以上の残業をしていてもメンタルヘルスは良好なままです。
一方、顧客や上司から要求される、自分の判断で仕事を処理し決定する権限(裁量権)のない残業は要注意です。
こちらの残業は依頼者の要求を深く慎重に考えなければいけませんし、高い集中が必要になります。とてもプレッシャーが高い働き方です。
とはいえ、この残業は自発的な動機で行われているわけではありません。
心身の疲労がとても高くなれば、どこかで(仕事に穴を開けないように)上手に手を抜いて疲労を軽減するように努めます。自分の健康を守るために。
これができる状態が「心が健康な状態」、すなわち「生存確率を上げる行動を選択している状態」ということですね。
◇◇◇◇
問題となるのは自発的な残業のほうです。仕事が好きでエネルギッシュに働く人です。月に100~200時間の残業も楽々とこなします。
しかし、このような人は脳からの出血や突然の心停止で命を落とすことがあります。これがいわゆる「過労による突然死」ですね。
一方で、メンタルヘルスで最も問題となるのは、「不安が原動力になっている長時間残業」です。
顧客も上司も同僚も、誰も望んでいないのに、自分だけが「もっとやらなければダメだ!」、「できないと大変なことになる!」と信じて疑わないケースです。
こちらは、とても強力な自発的動機で残業していますので、絶対に手を抜きません。
体力が限界を迎えても残業をやめようとしませんので、元々備わっている自己防衛本能が正常に働いて、強制的に残業にストップをかけてくれます。
それが抑うつ状態、具体的には憂鬱や意欲低下という負の感情です。
◇◇◇◇
あれ?このパートは職場の要因を説明するパートのはずでした。
ところが、長時間労働によるメンタルヘルス不調の大部分は、個人的な要因が大きいというところに戻ってしまいました。
このことが意味するのは絶望ではありません。自分自身で対処が可能であるという希望です。
そして睡眠時間が1日6時間を下回ると、メンタルヘルスが悪化し始めることが分かっています。
※出典:『過重労働とメンタルヘルス~特に長時間労働とメンタルヘルス~』
残業する理由は様々です。上司からの命令の場合もありますし、顧客からの要求の場合もあります。あるいは、お小遣い稼ぎのための残業もあります。
悲しい話ですが、職場しか居場所がなく、帰宅したくないから残業しているという人もいます(あまり褒められる働き方ではありません)。
このようなダラダラ残業は必死に働いているわけではありませんのでほとんど疲れません。
したがって月に50時間以上の残業をしていてもメンタルヘルスは良好なままです。
一方、顧客や上司から要求される、自分の判断で仕事を処理し決定する権限(裁量権)のない残業は要注意です。
こちらの残業は依頼者の要求を深く慎重に考えなければいけませんし、高い集中が必要になります。とてもプレッシャーが高い働き方です。
とはいえ、この残業は自発的な動機で行われているわけではありません。
心身の疲労がとても高くなれば、どこかで(仕事に穴を開けないように)上手に手を抜いて疲労を軽減するように努めます。自分の健康を守るために。
これができる状態が「心が健康な状態」、すなわち「生存確率を上げる行動を選択している状態」ということですね。
◇◇◇◇
問題となるのは自発的な残業のほうです。仕事が好きでエネルギッシュに働く人です。月に100~200時間の残業も楽々とこなします。
しかし、このような人は脳からの出血や突然の心停止で命を落とすことがあります。これがいわゆる「過労による突然死」ですね。
一方で、メンタルヘルスで最も問題となるのは、「不安が原動力になっている長時間残業」です。
顧客も上司も同僚も、誰も望んでいないのに、自分だけが「もっとやらなければダメだ!」、「できないと大変なことになる!」と信じて疑わないケースです。
こちらは、とても強力な自発的動機で残業していますので、絶対に手を抜きません。
体力が限界を迎えても残業をやめようとしませんので、元々備わっている自己防衛本能が正常に働いて、強制的に残業にストップをかけてくれます。
それが抑うつ状態、具体的には憂鬱や意欲低下という負の感情です。
◇◇◇◇
あれ?このパートは職場の要因を説明するパートのはずでした。
ところが、長時間労働によるメンタルヘルス不調の大部分は、個人的な要因が大きいというところに戻ってしまいました。
このことが意味するのは絶望ではありません。自分自身で対処が可能であるという希望です。
※当事務所のカウンセリングの特徴と概要についてはこちらをご覧ください
※対面・オンラインでのカウンセリングのお問い合わせはこちらからどうぞ
パワーハラスメントとセクシャルハラスメント

職場のメンタルヘルスの中で最も深刻なのがハラスメントです。
特にパワーハラスメントは精神障害による労災認定件数(仕事が原因で精神障害になったと国が認めた件数)で常にトップを走っています。
セクシャルハラスメントの労災認定件数は例年3位~5位を誇っています。
入社早々、新入社員の方を怖がらせることになってしまいますが、パワハラ、セクハラが一切発生しない職場はこの世に存在しません。必ず起こります。
なぜかというと、激ヤバなパワハラやセクハラというのは職場の文化・風土というより(これもありますがそれ以上に)、加害者のパーソナリティに大きく依存する問題だからです。
パワハラやセクハラを平気で行うような邪悪な人格(脳みそ)を持つ人間は、ある一定割合で必ずこの世に生まれてきます(人口の1~5%です)。
その割合と同じ割合で、あなたが飛び込んだ組織にも、激ヤバなハラスメント人間が必ず入り込んできているのです。
残念ながら、皆さんは近いうちにハラスメントを見たり聞いたりするでしょうし、深刻さは様々でしょうが、そのうちに実際に被害を受けることになるでしょう。
ハラスメントに関しては、「自分の身にいつでも起こり得る」という視点で対策を考えることが重要です。
◇◇◇◇
ハラスメントを受けて、「悪いのは自分だ」と考える人はメンタルヘルスを悪化させるリスクが極めて高くなります。
そして、「悪いのは自分」と考えているため、「自分一人で解決しなければ」と信じてしまい、誰にも相談をしなくなります。これが、行動が不合理になっているということですね。
こうなると、残念ながら自力での解決は難しくなります。もしこういう同僚を見かけたら、「行動が不合理になってない?相談に乗るよ」と声を掛けてあげてください。
また、ハラスメントには自分だけで対処することはできませんので、被害に遭ったら直ちに信頼できる人や、しかるべき窓口に相談してください。
具体的な対処法については以下の記事も併せてご覧ください。
▶パワーハラスメントの詳細についてはこちら
▶セクシャルハラスメントの詳細についてはこちら
特にパワーハラスメントは精神障害による労災認定件数(仕事が原因で精神障害になったと国が認めた件数)で常にトップを走っています。
セクシャルハラスメントの労災認定件数は例年3位~5位を誇っています。
※出典:令和5年度『精神障害に関する事案の労災補償状況』厚生労働省
入社早々、新入社員の方を怖がらせることになってしまいますが、パワハラ、セクハラが一切発生しない職場はこの世に存在しません。必ず起こります。
なぜかというと、激ヤバなパワハラやセクハラというのは職場の文化・風土というより(これもありますがそれ以上に)、加害者のパーソナリティに大きく依存する問題だからです。
パワハラやセクハラを平気で行うような邪悪な人格(脳みそ)を持つ人間は、ある一定割合で必ずこの世に生まれてきます(人口の1~5%です)。
その割合と同じ割合で、あなたが飛び込んだ組織にも、激ヤバなハラスメント人間が必ず入り込んできているのです。
残念ながら、皆さんは近いうちにハラスメントを見たり聞いたりするでしょうし、深刻さは様々でしょうが、そのうちに実際に被害を受けることになるでしょう。
ハラスメントに関しては、「自分の身にいつでも起こり得る」という視点で対策を考えることが重要です。
◇◇◇◇
ハラスメントを受けて、「悪いのは自分だ」と考える人はメンタルヘルスを悪化させるリスクが極めて高くなります。
そして、「悪いのは自分」と考えているため、「自分一人で解決しなければ」と信じてしまい、誰にも相談をしなくなります。これが、行動が不合理になっているということですね。
こうなると、残念ながら自力での解決は難しくなります。もしこういう同僚を見かけたら、「行動が不合理になってない?相談に乗るよ」と声を掛けてあげてください。
また、ハラスメントには自分だけで対処することはできませんので、被害に遭ったら直ちに信頼できる人や、しかるべき窓口に相談してください。
具体的な対処法については以下の記事も併せてご覧ください。
▶パワーハラスメントの詳細についてはこちら
▶セクシャルハラスメントの詳細についてはこちら
※当事務所のカウンセリングの特徴と概要についてはこちらをご覧ください
※対面・オンラインでのカウンセリングのお問い合わせはこちらからどうぞ
時限爆弾(未処理業務の蓄積)

仕事を引き受けたはいいのですが、引き受け過ぎてどれも中途半端にしか手を付けられず、仕事が溜まっていくことがあります。
期限の迫った未処理業務がたくさん溜まってくると、自分の力だけでは期限までに終わらせることができなくなります。
断ることが苦手で、何でも笑顔で引き受けてしまう方は要注意です。
複数の業務が塩漬け状態になり発酵し、最終的に「時限爆弾」と化していきます。この様な状況に陥ると出勤するのがとても怖くなります。
「時限爆弾」の恐ろしさを甘く見てはいけません。怖さのあまり、出勤しなくて済むように次のようなプチ妄想が出てくることすらあります。
□自分の乗っている通勤電車が脱線事故を起こして救急車で運ばれないかなぁ
□ミサイルや隕石が会社に命中して出勤できなくならないかなぁ
□仕事の提出先の人が急死しないかなぁ etc.
「時限爆弾」の威力は絶大で、ただこれだけが原因でメンタルヘルスが悪化し、休職してしまう人がいるくらいです。本当ですよ。
サラリーマンたるもの、なぜこれほどまで必死に働いているかといえば、それは「時限爆弾」を抱え込まないためです。
そのために残業をしたり、エネルギーを使って好きでもない人と根気よく業務の調整をしたり、時には仕事を断り喧嘩をしたりしているのです。いじらしいですね。
新入社員の方たちへの忠告です。「時限爆弾」を抱え込まないように細心の注意を払ってください。
もしたくさん抱え込んでどうしようもなくなったら、それに気づいた時点で直ぐに(とにかく早めに!)白旗を上げてください。
「期限が迫っていますが、これとこれとこれができていません!申し訳ありません!!」と上司に報告してください。
当然のごとく叱られますが、本当に期限が迫り、憂鬱になり、出勤できなくなり、休職するよりは百倍マシです。白旗を上げた日の夜はぐっすり眠れますよ。
期限の迫った未処理業務がたくさん溜まってくると、自分の力だけでは期限までに終わらせることができなくなります。
断ることが苦手で、何でも笑顔で引き受けてしまう方は要注意です。
複数の業務が塩漬け状態になり発酵し、最終的に「時限爆弾」と化していきます。この様な状況に陥ると出勤するのがとても怖くなります。
「時限爆弾」の恐ろしさを甘く見てはいけません。怖さのあまり、出勤しなくて済むように次のようなプチ妄想が出てくることすらあります。
□自分の乗っている通勤電車が脱線事故を起こして救急車で運ばれないかなぁ
□ミサイルや隕石が会社に命中して出勤できなくならないかなぁ
□仕事の提出先の人が急死しないかなぁ etc.
「時限爆弾」の威力は絶大で、ただこれだけが原因でメンタルヘルスが悪化し、休職してしまう人がいるくらいです。本当ですよ。
サラリーマンたるもの、なぜこれほどまで必死に働いているかといえば、それは「時限爆弾」を抱え込まないためです。
そのために残業をしたり、エネルギーを使って好きでもない人と根気よく業務の調整をしたり、時には仕事を断り喧嘩をしたりしているのです。いじらしいですね。
新入社員の方たちへの忠告です。「時限爆弾」を抱え込まないように細心の注意を払ってください。
もしたくさん抱え込んでどうしようもなくなったら、それに気づいた時点で直ぐに(とにかく早めに!)白旗を上げてください。
「期限が迫っていますが、これとこれとこれができていません!申し訳ありません!!」と上司に報告してください。
当然のごとく叱られますが、本当に期限が迫り、憂鬱になり、出勤できなくなり、休職するよりは百倍マシです。白旗を上げた日の夜はぐっすり眠れますよ。
※当事務所のカウンセリングの特徴と概要についてはこちらをご覧ください
※対面・オンラインでのカウンセリングのお問い合わせはこちらからどうぞ
知識や技術の不足
これは、仕事を依頼されたが、何をどうしていいか全く分からない状況のことです。
注意していただきたいのは、知識や技術の不足それ自体が精神疾患に繋がるわけではありません。
知識や技術が足りていないと認識したときに選択する行動によってメンタルヘルスが悪化します。
知識や技術が不足していることは何ら恥ずかしいことではありません。知らないだけなのですから、これから吸収していけばいいだけの話です。
新人なのですから、初めてのことでも「やってみます!」という積極性はもちろん大切です。
しかしいざ手を付けてみたら、「ぜんぜん分からない」ときにどうするかが重要になります。
自分の能力を最大限に使って調べても分からないのであれば、その業務が「時限爆弾」と化す前に、次のような趣旨で上司に相談してください。
「私にはこの業務を処理するための知識と技術が足りていません。業務を前に進めることができずに困っています。助けてください」
まともな上司であれば、教育として解決のヒントを与えてくれたり、あるいは解決方法を教えてくれたりします。新人なのだから知識がないのは当然です。
知識がないのに偉そうにしているのは無能の証拠で言語道断ですが、そうではなく、「今は分からない。助けてほしい」と相談することは許されます。
最悪の対処法は、「知らないことがバレたら無能と思われる!」と考えて、誰にも相談せずに一人で抱え込むことです。
「知らない=無能」という計算は誤りですがそれに気づいていません。誤った計算に基づいて採用する行動も誤りです。
その結果「時限爆弾」を抱え込むことになります。くれぐれも「時限爆弾」を抱え込まないように気をつけてください。
注意していただきたいのは、知識や技術の不足それ自体が精神疾患に繋がるわけではありません。
知識や技術が足りていないと認識したときに選択する行動によってメンタルヘルスが悪化します。
知識や技術が不足していることは何ら恥ずかしいことではありません。知らないだけなのですから、これから吸収していけばいいだけの話です。
新人なのですから、初めてのことでも「やってみます!」という積極性はもちろん大切です。
しかしいざ手を付けてみたら、「ぜんぜん分からない」ときにどうするかが重要になります。
自分の能力を最大限に使って調べても分からないのであれば、その業務が「時限爆弾」と化す前に、次のような趣旨で上司に相談してください。
「私にはこの業務を処理するための知識と技術が足りていません。業務を前に進めることができずに困っています。助けてください」
まともな上司であれば、教育として解決のヒントを与えてくれたり、あるいは解決方法を教えてくれたりします。新人なのだから知識がないのは当然です。
知識がないのに偉そうにしているのは無能の証拠で言語道断ですが、そうではなく、「今は分からない。助けてほしい」と相談することは許されます。
最悪の対処法は、「知らないことがバレたら無能と思われる!」と考えて、誰にも相談せずに一人で抱え込むことです。
「知らない=無能」という計算は誤りですがそれに気づいていません。誤った計算に基づいて採用する行動も誤りです。
その結果「時限爆弾」を抱え込むことになります。くれぐれも「時限爆弾」を抱え込まないように気をつけてください。
※当事務所のカウンセリングの特徴と概要についてはこちらをご覧ください
※対面・オンラインでのカウンセリングのお問い合わせはこちらからどうぞ
人間関係
私たちにとって最大かつ永遠のテーマでもある人間関係。
ストレッサー(ストレスの元)として最も強力でありながら、組織での対策が最も進んでいないのが人間関係です。
職場に限りませんが、私たちにとってのストレッサーには大きく分けて以下の3つがあります。
①物理的ストレッサー
②化学的ストレッサー
③心理社会的ストレッサー
物理的ストレッサーとは要するに、熱い冷たい、暑い寒い、広い狭い、高い深い、うるさい静か、眩しい暗い、臭い、角が当たって痛いなどです。
化学的ストレッサーとは有害な化学物質を浴びたり体内に取り込んだりすることです。
これら2つは、概ね同じくらいのレベルで同じような悪影響が誰に対しても出てきます。そう、個人差がとても小さいのです。測定も簡単です。
したがって、厚生労働省から発行されている「労働安全衛生規則」などで細かくルールが定められています。
皆さんが働くうえで、健康を害するほどの物理的ストレッサーや化学的ストレッサーに悩まされることは、今の日本ではほとんどないといってもよいでしょう。
さて、肝心の「人間関係」はどこに行ったのかというと、それが心理社会的ストレッサーです。
そして心理社会的ストレッサーは他の2つと違い、個人差が極めて大きいため、一律のルールが設定できないという致命的な欠点があります。
例えば、Aさんというひとりの人物との相性にしても、ある人は大好きでも、別のある人にとっては生理的に絶対無理ということがあり得るくらいに個人差が大きいのです。
ありがたい指導と捉えるかパワハラと捉えるか、愛の告白と捉えるかセクハラと捉えるかも人によってバラバラです。
しかし実際に困っている人がいるのだから何とかしようという社会的な機運が高まり、セクハラ防止法やマタハラ防止法、そしてパワハラ防止法が2007年から2020年にかけてやっと施行されました。
とはいえ捉え方に個人差があるために、残念ながらこれらの防止法はとても曖昧な内容となっています。
組織の人間関係への法的な対策は、この個人差の大きさも手伝って一番遅れています。というか対策は不可能かもしれません。
やっぱり人間関係は人類永遠のテーマですね。
ストレッサー(ストレスの元)として最も強力でありながら、組織での対策が最も進んでいないのが人間関係です。
職場に限りませんが、私たちにとってのストレッサーには大きく分けて以下の3つがあります。
①物理的ストレッサー
②化学的ストレッサー
③心理社会的ストレッサー
物理的ストレッサーとは要するに、熱い冷たい、暑い寒い、広い狭い、高い深い、うるさい静か、眩しい暗い、臭い、角が当たって痛いなどです。
化学的ストレッサーとは有害な化学物質を浴びたり体内に取り込んだりすることです。
これら2つは、概ね同じくらいのレベルで同じような悪影響が誰に対しても出てきます。そう、個人差がとても小さいのです。測定も簡単です。
したがって、厚生労働省から発行されている「労働安全衛生規則」などで細かくルールが定められています。
皆さんが働くうえで、健康を害するほどの物理的ストレッサーや化学的ストレッサーに悩まされることは、今の日本ではほとんどないといってもよいでしょう。
さて、肝心の「人間関係」はどこに行ったのかというと、それが心理社会的ストレッサーです。
そして心理社会的ストレッサーは他の2つと違い、個人差が極めて大きいため、一律のルールが設定できないという致命的な欠点があります。
例えば、Aさんというひとりの人物との相性にしても、ある人は大好きでも、別のある人にとっては生理的に絶対無理ということがあり得るくらいに個人差が大きいのです。
ありがたい指導と捉えるかパワハラと捉えるか、愛の告白と捉えるかセクハラと捉えるかも人によってバラバラです。
しかし実際に困っている人がいるのだから何とかしようという社会的な機運が高まり、セクハラ防止法やマタハラ防止法、そしてパワハラ防止法が2007年から2020年にかけてやっと施行されました。
とはいえ捉え方に個人差があるために、残念ながらこれらの防止法はとても曖昧な内容となっています。
組織の人間関係への法的な対策は、この個人差の大きさも手伝って一番遅れています。というか対策は不可能かもしれません。
やっぱり人間関係は人類永遠のテーマですね。
※当事務所のカウンセリングの特徴と概要についてはこちらをご覧ください
※対面・オンラインでのカウンセリングのお問い合わせはこちらからどうぞ
職場で顕在化する主な精神疾患

ここからは、新入社員の方が陥りやすいメンタルヘルス不調と精神疾患について見ていきましょう。
メンタルヘルス不調と精神疾患について
ここで用語を整理しておきます。
まずメンタルヘルス不調について。これは精神疾患だけでなく、広く心が不健康な状態を示しています。
具体的には、先ほどメンタルヘルス不調の定義で見たように、「不合理な行動に気づけなくなっている状態」のことです。
それに対して精神疾患とは(特にストレス反応性の精神疾患とは)、上記の不合理な行動をストップさせるための、「あるカテゴリー(診断基準)に当てはまった状態」のことをいいます。
メンタルヘルス不調と精神疾患のどちらが深刻かと言えば、当然、精神疾患です。
ということでここからは、ストレス反応性の精神疾患について詳しく見ていくことにしましょう。
なお、統合失調症や内因性うつ病、双極性障害などは、ストレスに関係なく発症する脳の病気ですから、この記事では扱っていません。
これらの病気について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
▶『仕事で精神疾患になるということ|種類と原因、診断と対応方法について』
まずメンタルヘルス不調について。これは精神疾患だけでなく、広く心が不健康な状態を示しています。
具体的には、先ほどメンタルヘルス不調の定義で見たように、「不合理な行動に気づけなくなっている状態」のことです。
それに対して精神疾患とは(特にストレス反応性の精神疾患とは)、上記の不合理な行動をストップさせるための、「あるカテゴリー(診断基準)に当てはまった状態」のことをいいます。
メンタルヘルス不調と精神疾患のどちらが深刻かと言えば、当然、精神疾患です。
ということでここからは、ストレス反応性の精神疾患について詳しく見ていくことにしましょう。
なお、統合失調症や内因性うつ病、双極性障害などは、ストレスに関係なく発症する脳の病気ですから、この記事では扱っていません。
これらの病気について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
▶『仕事で精神疾患になるということ|種類と原因、診断と対応方法について』
※当事務所のカウンセリングの特徴と概要についてはこちらをご覧ください
※対面・オンラインでのカウンセリングのお問い合わせはこちらからどうぞ
抑うつ状態
先ほど紹介したメンタルヘルス不調の定義から精神疾患を除いたものの中で、精神症状が出始めている状態が抑うつ状態です。
すなわち抑うつ状態とは、正常な心身のストレス反応のことです。
恋人に振られて気分が落ち込み、自責的になり、食欲が落ちるのは抑うつ状態です。
激しいパワハラを受けて眠れなくなり、気分が落ち込み、不安が強くなり、会社に行けなくなるのも抑うつ状態です。
どちらも正常な心身の反応です。
抑うつ状態とはその名の通り状態を表しているだけであり病名ではありません。インフルエンザや新型コロナウイルス感染症の初期に「発熱状態」と診断しているようなものです。
結局、何も診断していないということになります。自律神経失調症も同じですね。
しかし、正式な診断名でないものが、どうして精神科領域では使われているのでしょうか。
抑うつ状態や自律神経失調症という診断で会社を休職することも可能です。なぜでしょうか。
先ほど、抑うつ状態を放置して心身の機能に破綻が起きると精神疾患が発動するとお伝えしました。
抑うつ状態が生じていることを知った治療者は、その後どのような精神疾患に移行するかを待ちません。早めに対処します。
なぜかというと、最悪の場合本物のうつ病に移行する可能性があるからです。
「本物の」と敢えて書かなければならないほど、うつ病は誤解されています。うつ病は心の風邪なんかではありません。とても重い精神疾患です。
自殺のリスクがとても高いですし、リハビリを行えるようになるまでに数年を要することもあるなど、治療に長い長い時間が掛かります。
思考力が完全に元に戻ることはありませんし、数年にわたって倦怠感が続くこともあります。
恋人に振られて気分が落ち込み食欲がない人(抑うつ状態)に、休職の診断書を出す医者はさすがにいないと思います。
一方で、激しいパワハラが原因で気分が落ち込んでいる人(こちらも抑うつ状態)に対しては、休職の診断書の発行も考えます。
なぜなら失恋は、出勤が直接精神疾患を発動させる原因になる可能性が低いのに対して、パワハラは出勤を続けることによって精神疾患(重いうつ病)を発動させる可能性が極めて高いからです。
本物のうつ病を発症してしまったら大変です。職場が原因の抑うつ状態は、毎日職場に行かなければならない分、慎重に対処しなければなりません。
※「毎日職場に行かなければならない」という状況が、近代化による環境の激変ですね。縄文時代ではありえないことです。
すなわち抑うつ状態とは、正常な心身のストレス反応のことです。
恋人に振られて気分が落ち込み、自責的になり、食欲が落ちるのは抑うつ状態です。
激しいパワハラを受けて眠れなくなり、気分が落ち込み、不安が強くなり、会社に行けなくなるのも抑うつ状態です。
どちらも正常な心身の反応です。
抑うつ状態とはその名の通り状態を表しているだけであり病名ではありません。インフルエンザや新型コロナウイルス感染症の初期に「発熱状態」と診断しているようなものです。
結局、何も診断していないということになります。自律神経失調症も同じですね。
しかし、正式な診断名でないものが、どうして精神科領域では使われているのでしょうか。
抑うつ状態や自律神経失調症という診断で会社を休職することも可能です。なぜでしょうか。
先ほど、抑うつ状態を放置して心身の機能に破綻が起きると精神疾患が発動するとお伝えしました。
抑うつ状態が生じていることを知った治療者は、その後どのような精神疾患に移行するかを待ちません。早めに対処します。
なぜかというと、最悪の場合本物のうつ病に移行する可能性があるからです。
「本物の」と敢えて書かなければならないほど、うつ病は誤解されています。うつ病は心の風邪なんかではありません。とても重い精神疾患です。
自殺のリスクがとても高いですし、リハビリを行えるようになるまでに数年を要することもあるなど、治療に長い長い時間が掛かります。
思考力が完全に元に戻ることはありませんし、数年にわたって倦怠感が続くこともあります。
恋人に振られて気分が落ち込み食欲がない人(抑うつ状態)に、休職の診断書を出す医者はさすがにいないと思います。
一方で、激しいパワハラが原因で気分が落ち込んでいる人(こちらも抑うつ状態)に対しては、休職の診断書の発行も考えます。
なぜなら失恋は、出勤が直接精神疾患を発動させる原因になる可能性が低いのに対して、パワハラは出勤を続けることによって精神疾患(重いうつ病)を発動させる可能性が極めて高いからです。
本物のうつ病を発症してしまったら大変です。職場が原因の抑うつ状態は、毎日職場に行かなければならない分、慎重に対処しなければなりません。
※「毎日職場に行かなければならない」という状況が、近代化による環境の激変ですね。縄文時代ではありえないことです。
※当事務所のカウンセリングの特徴と概要についてはこちらをご覧ください
※対面・オンラインでのカウンセリングのお問い合わせはこちらからどうぞ
不安症
不安の命じるままにとる行動のことを回避行動といいます。
回避行動を詳しく分析すると、とても不合理な行動なのですが、本人はその不合理さに全く気づきません。
回避行動をとり続けていると、そのうちに心身の機能が破綻します。その破綻を防ぐために自己防衛本能が働いて負の感情を生じさせます。
負の感情は、あなたを眠れなくしたり、布団から起き上がれなくしたり、出勤しにくくさせてくれます。
この状態で病院に行くと、多くは抑うつ状態と診断されます。
ところが不安からの命令が強くて出勤できない、大切な会議を欠席する、部屋から出られなくなるなど、日常生活に著しい困難が生じると不安症という診断が付きます。
これで精神疾患に罹患したことになります。
◇◇◇◇
不安症は、脳からの命令の種類によって複数の診断名が用意されています。
脳からの命令が、「あらゆる状況を警戒しろ。その不安をお前は全くコントロールできないぞ。だから仕事なんか放棄して、その不安の命じるままに行動せよ」というものであれば、全般不安症という診断になります。
※あらゆる状況を警戒しなくても何も悪いことは起きません。安心してください。
(とお伝えしても警戒してしまうのが全般不安症です)
脳からの命令が、「人前で大恥をかくぞ。失敗して笑いものになるぞ。だから人前でスピーチしたり、食事をしたりするな。会議も結婚式も欠席せよ」なら社交不安症です。
※人前で失敗しても致命的な恥はかきません。そもそも失敗するかどうかも分かりません。だから安心してください。
(とお伝えしても恥をかくと信じて疑わないのが社交不安症です)
脳からの命令が、「以前パニック発作を起こしただろう。そこに行けばまたパニック発作を起こすぞ。パニック発作を起こして死ぬかもしれないぞ。だから外に出るな」がパニック症です。
※パニック発作を起こして死ぬことは絶対にありません。安心してください。
(とお伝えしても死ぬのではないかと思うのがパニック症です)
回避行動を詳しく分析すると、とても不合理な行動なのですが、本人はその不合理さに全く気づきません。
回避行動をとり続けていると、そのうちに心身の機能が破綻します。その破綻を防ぐために自己防衛本能が働いて負の感情を生じさせます。
負の感情は、あなたを眠れなくしたり、布団から起き上がれなくしたり、出勤しにくくさせてくれます。
この状態で病院に行くと、多くは抑うつ状態と診断されます。
ところが不安からの命令が強くて出勤できない、大切な会議を欠席する、部屋から出られなくなるなど、日常生活に著しい困難が生じると不安症という診断が付きます。
これで精神疾患に罹患したことになります。
◇◇◇◇
不安症は、脳からの命令の種類によって複数の診断名が用意されています。
脳からの命令が、「あらゆる状況を警戒しろ。その不安をお前は全くコントロールできないぞ。だから仕事なんか放棄して、その不安の命じるままに行動せよ」というものであれば、全般不安症という診断になります。
※あらゆる状況を警戒しなくても何も悪いことは起きません。安心してください。
(とお伝えしても警戒してしまうのが全般不安症です)
脳からの命令が、「人前で大恥をかくぞ。失敗して笑いものになるぞ。だから人前でスピーチしたり、食事をしたりするな。会議も結婚式も欠席せよ」なら社交不安症です。
※人前で失敗しても致命的な恥はかきません。そもそも失敗するかどうかも分かりません。だから安心してください。
(とお伝えしても恥をかくと信じて疑わないのが社交不安症です)
脳からの命令が、「以前パニック発作を起こしただろう。そこに行けばまたパニック発作を起こすぞ。パニック発作を起こして死ぬかもしれないぞ。だから外に出るな」がパニック症です。
※パニック発作を起こして死ぬことは絶対にありません。安心してください。
(とお伝えしても死ぬのではないかと思うのがパニック症です)
※当事務所のカウンセリングの特徴と概要についてはこちらをご覧ください
※対面・オンラインでのカウンセリングのお問い合わせはこちらからどうぞ
適応障害

職場に行くのがつらくなって精神科のクリニックへ行くと、猫も杓子も適応障害という診断をつけられます。
その理由は、適応障害の診断基準の中に、「明確なストレス要因があり、その要因から離れると症状が消える」というものがあり、これが拡大解釈されているからです。
明確なストレスが原因の一般的な体調不良は、そのストレスから離れれば症状は治まります。そんなの当たり前です。
これを適応障害の診断に適用してしまっているのです。
ある精神科医がテレビに出演し、こんなことを話していました。
「明確なストレスによって発症し、そのストレスから離れると症状が治まるのであれば、それは適応障害であり、医学的にも認められている」
これでは視聴者に誤解を与えてしまいます。そう、単なるストレス性の体調不良と精神疾患がゴッチャになっているのです。
適応障害と診断されるには、そのストレスに比べて症状が過剰でなければなりません。
「そんなストレスを受けたらきっと体調を崩すよね」と了解できるものに適応障害の診断はつけられません。
「そのストレスでどうしてそうなっちゃうの?」という状況が必要です。このような状況のことを私たちは「了解不能」と表現します。
私はこれまで“適応障害”と診断されている数多くの方と接してきましたが、本物の適応障害に出会ったのは数えるほどしかありません。
そのうちの3つのケースをご紹介しましょう。
①ひとつめは、健康診断で要精密検査の項目があり、それを知った日から強い憂鬱が生じ、1週間以上全く眠れなくなり、なぜか家族に怒りをぶちまけるという症状が出現しました。
精神科クリニックを受診して会社を休職し、強い薬を使って眠れるようにしてもらいました。
後日、体の精密検査を受けたところ結果は「異常なし」でした。その日から精神症状は全て消えてしまいました。
②ふたつめは、コロナ禍による緊急事態宣言でテレワークに入った途端、この方も全く眠れなくなり、強い不安と憂鬱が生じて何もできなくなってしまいました。
「びっくりするくらい何もできなくなった」と話していました。この方も休職し、仕事から離れると症状はきれいさっぱり消えてしまいました。
③三つめは、プロジェクトリーダーに抜擢され業務量も責任も格段に増えた結果、自宅の部屋の中で暴れ、家具を破壊し、掛け布団を破って部屋中に羽毛をぶちまけました。
この方も休職した途端、症状は治まってしまいました。
私はこの方たちに、「なぜそんなに強い症状が急激に出現したのでしょう。何か思い当たる原因はありますか?」と質問しましたが、三人とも、「なぜそうなったか分からない」と話していました。
これらが本物の(というか普通の)適応障害の症状です。
というわけで、本物の(普通の)適応障害とは、なってみないと分からない病気です。何がきっかけになって発症するのか、本人にも事前には全く分かりません。
最も印象に残っているケースとして、オフィスの席替えが原因で出勤できなくなった方がいました(席を元の場所に戻したら直ぐに出勤しました)。
実は適応障害とは、本人も治療者も、「何が何だか分からない」、「そんなことってふつうある?」という精神疾患です。了解不能なのです。
逆に言うと了解不能でなければ適応障害の診断はつけられません(本当は)。
その理由は、適応障害の診断基準の中に、「明確なストレス要因があり、その要因から離れると症状が消える」というものがあり、これが拡大解釈されているからです。
明確なストレスが原因の一般的な体調不良は、そのストレスから離れれば症状は治まります。そんなの当たり前です。
これを適応障害の診断に適用してしまっているのです。
ある精神科医がテレビに出演し、こんなことを話していました。
「明確なストレスによって発症し、そのストレスから離れると症状が治まるのであれば、それは適応障害であり、医学的にも認められている」
これでは視聴者に誤解を与えてしまいます。そう、単なるストレス性の体調不良と精神疾患がゴッチャになっているのです。
適応障害と診断されるには、そのストレスに比べて症状が過剰でなければなりません。
「そんなストレスを受けたらきっと体調を崩すよね」と了解できるものに適応障害の診断はつけられません。
「そのストレスでどうしてそうなっちゃうの?」という状況が必要です。このような状況のことを私たちは「了解不能」と表現します。
私はこれまで“適応障害”と診断されている数多くの方と接してきましたが、本物の適応障害に出会ったのは数えるほどしかありません。
そのうちの3つのケースをご紹介しましょう。
①ひとつめは、健康診断で要精密検査の項目があり、それを知った日から強い憂鬱が生じ、1週間以上全く眠れなくなり、なぜか家族に怒りをぶちまけるという症状が出現しました。
精神科クリニックを受診して会社を休職し、強い薬を使って眠れるようにしてもらいました。
後日、体の精密検査を受けたところ結果は「異常なし」でした。その日から精神症状は全て消えてしまいました。
②ふたつめは、コロナ禍による緊急事態宣言でテレワークに入った途端、この方も全く眠れなくなり、強い不安と憂鬱が生じて何もできなくなってしまいました。
「びっくりするくらい何もできなくなった」と話していました。この方も休職し、仕事から離れると症状はきれいさっぱり消えてしまいました。
③三つめは、プロジェクトリーダーに抜擢され業務量も責任も格段に増えた結果、自宅の部屋の中で暴れ、家具を破壊し、掛け布団を破って部屋中に羽毛をぶちまけました。
この方も休職した途端、症状は治まってしまいました。
私はこの方たちに、「なぜそんなに強い症状が急激に出現したのでしょう。何か思い当たる原因はありますか?」と質問しましたが、三人とも、「なぜそうなったか分からない」と話していました。
これらが本物の(というか普通の)適応障害の症状です。
というわけで、本物の(普通の)適応障害とは、なってみないと分からない病気です。何がきっかけになって発症するのか、本人にも事前には全く分かりません。
最も印象に残っているケースとして、オフィスの席替えが原因で出勤できなくなった方がいました(席を元の場所に戻したら直ぐに出勤しました)。
実は適応障害とは、本人も治療者も、「何が何だか分からない」、「そんなことってふつうある?」という精神疾患です。了解不能なのです。
逆に言うと了解不能でなければ適応障害の診断はつけられません(本当は)。
※当事務所のカウンセリングの特徴と概要についてはこちらをご覧ください
※対面・オンラインでのカウンセリングのお問い合わせはこちらからどうぞ
発達障害傾向について
発達障害は生まれつきの脳の機能障害です(乳幼児期の心理的・化学的ストレスが原因という説もあります)。
したがって、仕事のストレスが原因で発達障害を発症するわけではありません。
実態としては、発達障害に特有の言動が原因でいじめや激しい叱責を受けてしまい、その結果として二次的に抑うつ状態や適応障害を発症しています。
発達障害の特徴には以下のようなものがあります。
ADHD傾向
■忘れ物が多い
■大切な用事を忘れてしまう
■物を失くしやすい
■待つことが苦手で衝動的な行動を抑えられない etc.
ASD傾向
■雑談が苦手(場の空気が読めない)
■言葉を字面通りに受け取ってしまう(行間が読めない)
■相手の気持ちを読み取るのが難しい
■物の配置や日々の行動に強いこだわりがある
■社交的という意味が分からない
■味覚、聴覚、嗅覚、触覚などが過敏 etc.
これだけではありませんが代表的なものを挙げておきました。
これらに該当する方は、いわゆる「大人の発達障害」の傾向を持っている可能性があります。
学生時代と違い、これらの特性が業務上では極めて深刻な問題を生じさせることになります。
自分では理由が全く分からないのに急に激しく叱責される場合は要注意です。専門家への相談も考えましょう。
理由が全く分からず、不意を突かれて激しく叱責されることはとても怖いものです。常にビクビクしてしまい仕事どころではなくなってしまいます。
したがって、仕事のストレスが原因で発達障害を発症するわけではありません。
実態としては、発達障害に特有の言動が原因でいじめや激しい叱責を受けてしまい、その結果として二次的に抑うつ状態や適応障害を発症しています。
発達障害の特徴には以下のようなものがあります。
ADHD傾向
■忘れ物が多い
■大切な用事を忘れてしまう
■物を失くしやすい
■待つことが苦手で衝動的な行動を抑えられない etc.
ASD傾向
■雑談が苦手(場の空気が読めない)
■言葉を字面通りに受け取ってしまう(行間が読めない)
■相手の気持ちを読み取るのが難しい
■物の配置や日々の行動に強いこだわりがある
■社交的という意味が分からない
■味覚、聴覚、嗅覚、触覚などが過敏 etc.
これだけではありませんが代表的なものを挙げておきました。
これらに該当する方は、いわゆる「大人の発達障害」の傾向を持っている可能性があります。
学生時代と違い、これらの特性が業務上では極めて深刻な問題を生じさせることになります。
自分では理由が全く分からないのに急に激しく叱責される場合は要注意です。専門家への相談も考えましょう。
理由が全く分からず、不意を突かれて激しく叱責されることはとても怖いものです。常にビクビクしてしまい仕事どころではなくなってしまいます。
※当事務所のカウンセリングの特徴と概要についてはこちらをご覧ください
※対面・オンラインでのカウンセリングのお問い合わせはこちらからどうぞ
入社後の精神疾患を防ぐために

最後に精神疾患の予防と対策についてお伝えします。
早めに助けを求める(抑うつ状態)
抑うつ状態になるのを防ぐためには、睡眠状態を観察することが最も重要です。
寝付けない、夜中に何度も目が覚める、朝方目が覚めてそのあと眠れない、という症状が出現したら状況を注意深く観察してください。
「ある夜プレッシャーで全く眠れなくなり、睡眠不足のまま出勤してヘトヘトになって帰宅した。昨夜は全く眠れなかったのに、その夜は疲れも手伝ってぐっすり眠れた」
このような状況なら問題はありません。これは一過性の不眠です。
抑うつ状態の前駆症状の不眠は、どれだけ疲れていても、どれだけ眠くても眠れません。これが数日続きます。
先ずは睡眠障害の原因を考えてみましょう。先に挙げたプライベート要因や職場の要因がないかチェックしてみてください。
もし当てはまるものがあれば、早めに信頼できる人に相談して具体的に助けを求めましょう。
相談しなければと思ったときに、「相談しないで一人で解決しなければならない」などと考えているときこそ、勇気を振り絞って誰かに相談してください。
「相談しないほうが安全だ」という決断は不合理で間違っている可能性があります。
寝付けない、夜中に何度も目が覚める、朝方目が覚めてそのあと眠れない、という症状が出現したら状況を注意深く観察してください。
「ある夜プレッシャーで全く眠れなくなり、睡眠不足のまま出勤してヘトヘトになって帰宅した。昨夜は全く眠れなかったのに、その夜は疲れも手伝ってぐっすり眠れた」
このような状況なら問題はありません。これは一過性の不眠です。
抑うつ状態の前駆症状の不眠は、どれだけ疲れていても、どれだけ眠くても眠れません。これが数日続きます。
先ずは睡眠障害の原因を考えてみましょう。先に挙げたプライベート要因や職場の要因がないかチェックしてみてください。
もし当てはまるものがあれば、早めに信頼できる人に相談して具体的に助けを求めましょう。
相談しなければと思ったときに、「相談しないで一人で解決しなければならない」などと考えているときこそ、勇気を振り絞って誰かに相談してください。
「相談しないほうが安全だ」という決断は不合理で間違っている可能性があります。
※当事務所のカウンセリングの特徴と概要についてはこちらをご覧ください
※対面・オンラインでのカウンセリングのお問い合わせはこちらからどうぞ
不安を味わい尽くして行動する(不安症)
不安が強い場合の対処法は、とにかく不安を取り扱わないということに尽きます。
不安は強力に「まずいことになるからあれをしろ」とか「危険だからそれをするな」とあなたに命令してきます。
しかしその命令には何の根拠もありません。不安はフィクションであり、事実を何ら反映していません。
ですから、「不安を無視して今やるべきことをやる」だけで不安は消えていきます。これが不安への対処の結論となります。
不安は検討してはいけません。不安は味わうだけにしてください。
しかし、これがとても難しい。なぜなら、不安が強い人は、「この不安は事実を反映している」と信じて疑わないからです。
不安が強くて自分の力ではコントロールできないと感じる方は、早めに専門家に相談することをお勧めします。
不安の対処法は確立されていますので、専門家に相談すれば必ず不安を小さくすることができます。
不安は強力に「まずいことになるからあれをしろ」とか「危険だからそれをするな」とあなたに命令してきます。
しかしその命令には何の根拠もありません。不安はフィクションであり、事実を何ら反映していません。
ですから、「不安を無視して今やるべきことをやる」だけで不安は消えていきます。これが不安への対処の結論となります。
不安は検討してはいけません。不安は味わうだけにしてください。
しかし、これがとても難しい。なぜなら、不安が強い人は、「この不安は事実を反映している」と信じて疑わないからです。
不安が強くて自分の力ではコントロールできないと感じる方は、早めに専門家に相談することをお勧めします。
不安の対処法は確立されていますので、専門家に相談すれば必ず不安を小さくすることができます。
※当事務所のカウンセリングの特徴と概要についてはこちらをご覧ください
※対面・オンラインでのカウンセリングのお問い合わせはこちらからどうぞ
初発は防げません!(適応障害)
適応障害については、いきなり不都合な真実をお伝えしなければなりません。
それは、適応障害とは、なってみないと分からない精神疾患ですから、「最初の発症は防ぐことができない」ということです。
適応障害の発症を完全に防ぐためには、その人の身に現実に起こりうる環境変化を、事前に全て排除しておかなければなりません。そんなことは不可能です。
残念ながら初発は防げません。
一方で、ある環境変化によって適応障害(過剰で了解不能の行動)が生じたのであれば、今後はその環境変化に近づかなければよいということになります。
しかし、これはこれで簡単ではありません。
先ほどご紹介した事例でいえば、今後は健康診断を受けない、テレワークをしない、プロジェクトリーダーにならない、席替えをしないということになってしまいます。
私は本物の(普通の)適応障害に対処法はないのではないかと思っています。
過剰で了解不能な行動が出現するたびに、そのストレス源から離れるように対処していくしかありません。
実は、適応障害は原因も治療法も分かっていません。今後、適応障害に関する研究が進むことを願っています。
それは、適応障害とは、なってみないと分からない精神疾患ですから、「最初の発症は防ぐことができない」ということです。
適応障害の発症を完全に防ぐためには、その人の身に現実に起こりうる環境変化を、事前に全て排除しておかなければなりません。そんなことは不可能です。
残念ながら初発は防げません。
一方で、ある環境変化によって適応障害(過剰で了解不能の行動)が生じたのであれば、今後はその環境変化に近づかなければよいということになります。
しかし、これはこれで簡単ではありません。
先ほどご紹介した事例でいえば、今後は健康診断を受けない、テレワークをしない、プロジェクトリーダーにならない、席替えをしないということになってしまいます。
私は本物の(普通の)適応障害に対処法はないのではないかと思っています。
過剰で了解不能な行動が出現するたびに、そのストレス源から離れるように対処していくしかありません。
実は、適応障害は原因も治療法も分かっていません。今後、適応障害に関する研究が進むことを願っています。
※当事務所のカウンセリングの特徴と概要についてはこちらをご覧ください
※対面・オンラインでのカウンセリングのお問い合わせはこちらからどうぞ
カミングアウトがあなたを救う(発達障害傾向)

「大人の発達障害」という言葉が社会的に注目を集めるようになって10年近くが経過しました。
メディアに取り上げられたり、企業研修でも大人の発達障害がテーマになるなど、社会全体に認識されてきた実感があります。
何が認識されてきたかというと、「発達障害というのは生まれつきの特性であり個性である」ということです。
その結果、「社会が変われば、当事者の生きづらさは軽減されうる」という理解が浸透してきました。
企業の人事担当者と話していても、「ある社員が発達障害らしい。困った。何とかしてほしい!」といった声は、近年ほとんど聞かなくなりました。
ここ10年で、企業内でも大人の発達障害に関する認識が、(浅いかもしれませんが)広く浸透しているのでしょう。
こういった時代背景も踏まて、どうすれば発達障害傾向を持つ方がメンタルヘルス不調に陥ることなく、健やかに働き続けることができるかを考えてみましょう。
結論から申し上げると、もはや発達障害傾向は隠す必要がないのではないかということです。
私の臨床経験からも、抑うつ状態で休職したことをきっかけに自らの発達障害傾向を上司や同僚に打ち明けた方のほうが、スムーズに復職している印象を持っています。
特性を周囲に理解してもらったうえで、朗らかな性格や軽やかなフットワーク(ADHD)、高い記憶力や作業の正確性(ASD)など、得意な分野で活躍することが根本的な対策になると思います。
メディアに取り上げられたり、企業研修でも大人の発達障害がテーマになるなど、社会全体に認識されてきた実感があります。
何が認識されてきたかというと、「発達障害というのは生まれつきの特性であり個性である」ということです。
その結果、「社会が変われば、当事者の生きづらさは軽減されうる」という理解が浸透してきました。
企業の人事担当者と話していても、「ある社員が発達障害らしい。困った。何とかしてほしい!」といった声は、近年ほとんど聞かなくなりました。
ここ10年で、企業内でも大人の発達障害に関する認識が、(浅いかもしれませんが)広く浸透しているのでしょう。
こういった時代背景も踏まて、どうすれば発達障害傾向を持つ方がメンタルヘルス不調に陥ることなく、健やかに働き続けることができるかを考えてみましょう。
結論から申し上げると、もはや発達障害傾向は隠す必要がないのではないかということです。
私の臨床経験からも、抑うつ状態で休職したことをきっかけに自らの発達障害傾向を上司や同僚に打ち明けた方のほうが、スムーズに復職している印象を持っています。
特性を周囲に理解してもらったうえで、朗らかな性格や軽やかなフットワーク(ADHD)、高い記憶力や作業の正確性(ASD)など、得意な分野で活躍することが根本的な対策になると思います。
※当事務所のカウンセリングの特徴と概要についてはこちらをご覧ください
※対面・オンラインでのカウンセリングのお問い合わせはこちらからどうぞ
遺伝の影響ふたたび(精神疾患の家族を持つ方へ)
精神疾患の家族や親戚を持つ新入社員の方は、自分の中に現れる瞬間的な感情や、それに伴う行動を人一倍注意深く観察する必要があります。
うっかりしていると、自分が生存確率を下げる行動を選択してしまい、そのことに気づけなくなるかもしれないからです。
注意)生存確率を下げる行動というのは現代社会だからであり、縄文時代であれば生存確率を上げる、とても適応的な行動だった可能性があります。
精神疾患に関する遺伝子を多く受け継いでいる方がメンタルヘルスを良好に保つためには、とても月並みですが、規則正しい生活を送るということがとても重要になります。
寝る時間、起きる時間、食事の時間と回数、月の残業時間管理、適切な援助の要請、定期的な休養、定期的な余暇などです。
仕事の関係で規則正しい生活が送れなくなって体調の悪化を自覚したときには、必ず仕事に悪影響を与える前に、先輩や上司に相談してください。
私がお勧めしている相談を決断する目安は、眠いのに眠れない状況が3日以上続いた時です。
うっかりしていると、自分が生存確率を下げる行動を選択してしまい、そのことに気づけなくなるかもしれないからです。
注意)生存確率を下げる行動というのは現代社会だからであり、縄文時代であれば生存確率を上げる、とても適応的な行動だった可能性があります。
精神疾患に関する遺伝子を多く受け継いでいる方がメンタルヘルスを良好に保つためには、とても月並みですが、規則正しい生活を送るということがとても重要になります。
寝る時間、起きる時間、食事の時間と回数、月の残業時間管理、適切な援助の要請、定期的な休養、定期的な余暇などです。
仕事の関係で規則正しい生活が送れなくなって体調の悪化を自覚したときには、必ず仕事に悪影響を与える前に、先輩や上司に相談してください。
私がお勧めしている相談を決断する目安は、眠いのに眠れない状況が3日以上続いた時です。
※当事務所のカウンセリングの特徴と概要についてはこちらをご覧ください
※対面・オンラインでのカウンセリングのお問い合わせはこちらからどうぞ
まとめ

新入社員の方たちの約9割は精神疾患を発症しません。この記事の対象となる方は新入社員の中の約1割です。
記事に当てはまる1割に該当した方は、人一倍セルフケアに気をつけなければなりません。
実は、メンタルヘルス不調のセルフケアは簡単ではありません。とても難しいものです。
自分の健康を守るための行動を本能的に瞬時に選択できる人でなければ、自力での対処は難しいでしょう。
心配な方は専門家への相談も選択肢に入れておくとよいでしょう。
◇◇◇◇
他の健康管理と同じように、メンタルヘルス不調も精神疾患も、早期発見・早期治療が重要です。
もっと正確にお伝えしましょう。
早期発見・早期治療ではありませんね。ストレス反応性の精神疾患の場合は、「早期気づき・早期行動変容」です。
ストレス反応性の精神疾患は、新入社員のように若い人でも発症する生活習慣病です。日ごろから「早期気づき・早期行動変容」を心がけていきましょう!
記事に当てはまる1割に該当した方は、人一倍セルフケアに気をつけなければなりません。
実は、メンタルヘルス不調のセルフケアは簡単ではありません。とても難しいものです。
自分の健康を守るための行動を本能的に瞬時に選択できる人でなければ、自力での対処は難しいでしょう。
心配な方は専門家への相談も選択肢に入れておくとよいでしょう。
◇◇◇◇
他の健康管理と同じように、メンタルヘルス不調も精神疾患も、早期発見・早期治療が重要です。
もっと正確にお伝えしましょう。
早期発見・早期治療ではありませんね。ストレス反応性の精神疾患の場合は、「早期気づき・早期行動変容」です。
ストレス反応性の精神疾患は、新入社員のように若い人でも発症する生活習慣病です。日ごろから「早期気づき・早期行動変容」を心がけていきましょう!
※当事務所のカウンセリングの特徴と概要についてはこちらをご覧ください
※対面・オンラインでのカウンセリングのお問い合わせはこちらからどうぞ
投稿者プロフィール

- 精神保健福祉士/産業カウンセラー/ストレスチェック実施者資格/社会福祉施設施設長資格/教育職員免許
-
個人のお客様には、認知行動療法に基づくカウンセリングを対面およびオンラインで提供しています。全国からご利用可能です。
法人向けには、メンタルヘルス研修やストレスチェック、相談窓口の運営を含む包括的なサポートを行い、オンライン研修も対応。アンガーマネジメントやハラスメント研修も実施し、企業の健康的な職場環境づくりを支援します。